2010年11月26日
脳ブームの火付け役
先駆者として上げられる人物として
東北大学未来科学技術共同研究センター教授
川島隆太教授
は間違いなく上げられる人物であるだろう。
今回の本
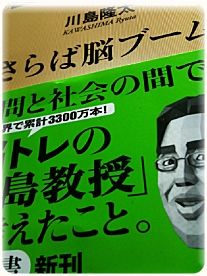
さらば脳ブーム (新潮新書)
川島 隆太
[詳細はAmazonで⇒ ]
]
では、
そんな、脳ブームの火付け役である
川島教授ご自身がこの脳ブームとの別れを
書くようなタイトルな本なわけだが
果たして、その真意とはなんなのでしょうか・・・
先駆者として上げられる人物として
東北大学未来科学技術共同研究センター教授
川島隆太教授
は間違いなく上げられる人物であるだろう。
今回の本
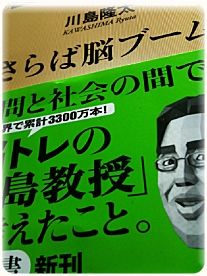
さらば脳ブーム (新潮新書)
川島 隆太
[詳細はAmazonで⇒
 ]
]では、
そんな、脳ブームの火付け役である
川島教授ご自身がこの脳ブームとの別れを
書くようなタイトルな本なわけだが
果たして、その真意とはなんなのでしょうか・・・
【目次】
【書感】
川島教授といえば
ニンテンドーDSを持っている人であれば、このソフトを知らない人はいないのではないだろうか。

この「脳トレ」がどのように出来ていったのか、
脳トレによる「脳」ブームの功罪
そして、今の脳ブームへの喝
といった3つの視点で今回は紐解いていこうと思う。
努力すればなんとかなるという域。
後者は、新しい場面や局面に対応する能力。遺伝子によって
規定されている生まれつきの能力で、20歳を過ぎたころに低下していくそうだ。
で、この流動性が確保される領域がワーキングメモリーである。
読み書きというのもこのワーキングメモリーが必要な作業で
トレーニングすることによってワーキングメモリーを鍛えることができる
と大まかに言ってしまえば、この発想から「脳トレ」は生まれている。
この読み書きを計算することによって脳を鍛えることができるのでは?
という試みを発達障害児、認知症の方たちに
向けて取り組んだということが本書には書かれている。
医療機関に行って最初に専門家たち
学習療法(読み書き計算)を取り入れようと病院へお願いするのだが
介護のプロたちには非常に冷徹な眼で見られる
「そんなことしても無駄でしょう」
って、このことはどんな研究や発明にも共通するのかもしれないですけど
最初から沢山の人々に理解されることは無い
ということなのかなと感じる。
で、いざやってみると認知症の患者さんたちは
喜んで取り組み始め、療法を続けていくうちに
問題を解く喜びを覚えたり
ある人はおしゃれをするようになったり
ある人は自律的に活動するようになったりと
凄まじい効果があったそうだ。
蓋を開けてみると川島教授の評価も「詐欺師」が「教祖様」だったそうだ。
これも新たな発明の現場では結構目につく出来事なのかもしれないけれども。
大人のドリルがあれば子供が机に向かっているときに大人も一緒に
解くことができる。
こういう発想が元になって、
「大人のドリル」という形で公文から発売された

このシリーズは累計400万部を突破したらしく
ドリルの内容がデータを根拠にきちんと説明されていたことや
狙い通りの子供と親の意思疎通のツールとして子供との会話が増えたなんて声も聞こえてきたり
ゆとり教育の見直しのための「朝のモジュールタイム」などの活動と偶然時期が重なったと本書では語られている。
中には、うまく導入はできたものの、高齢者の夫婦間では
こんなドリルみたいなものを俺に解かせるのか
と、プライドを逆なでてしまい、余計に認知症が悪化していった
なんて例も見られたそうだ。
これは支援者と学習者と共に学習療法を行い、学習者が教材が解けたことを
認め、お互い喜び、機会があれば教材を元に会話をするということができれば
問題のないことなのだが、伝わり方、手順が誤ってしまえば、その効果が発揮できない
という一面もあり、ちゃんとしたシステムが出来ていても
その利用方法をしっかり伝達するツール、仕組みができないと
我々が日々接している仕事という面と何ら変りないことなのかなとも感じてしまった。
とまぁ失敗の例もあるわけだが、ここから冒頭に紹介した
DSのゲームにつながっていく。
任天堂の岩田社長がDSの発売日に川島教授の研究室に訪れたなんて
エピソードが書かれている。
川島教授と岩田社長が同い年であったこと
DSと相性が良さそうということで共感し発売に至るわけである。
ただし、2点ほど落とし穴をつくったまま展開をしてしまったとも認めていて
まず、
まぁここまで「脳トレ」が流行ることは想像もしていなかったということが書かれている。
もう一つは単純化した情報の露出
このあたりの苦労話は少々著者の愚痴っぽくなっているが
相当苦労したように見受けられるので本書を読んでね。に譲ろうと思う。
ただ、素晴らしいことはソフトの売上から入ってくる収入を個人としては一切受け取っておらず、
自分が所属する東北大学に管理してもらっているらしくビルが2棟もたったというから驚きである。
しかも、2本のDSソフトとは趣旨が異なる自分の能力向上を図る新しいソフトが2010年末に発売になる
という宣伝まで書いてある、非常に自身に満ち溢れて宣伝されているのでちょっとやってみたくもなる。
川島教授は本書で「脳科学者」と名乗っている人たちを次のようにたたっ斬っている。
そうなると、ちょっと待って欲しい。
その情報を手にする我々に
何を信じればいいのか?
となってしまうわけである。
研究を生業にしていて、
研究に9割力を割くという研究者の方達の意見は十分わかる。
ただ、世間に伝えるために
そういったプロフェッショナルな方達が、特にニッチな分野なら尚更
しっかりと世間にメッセージを伝えてくれなければ
その研究されている方から見た
「ジャーナリスト」だとか「芸脳人」だとかが更にのさばっていくのでは
ないだろうか?
ブログだったり、Twitterだったりで
自分のメディアを持てる時代であるのだから、その1割を使って
自分メディアにパワーを割き、我々にマスゴミを通さず
真実を伝えて頂きたいものである。
学会は確かに大切かもしれない。
ただ、学会だけ、ネットなんて価値のない空間に展開しても
意味が無いなんて狭義な考え方は是非とも止めて頂きたい。
確かに、人が脳について、考えることについて学ぶようになったことは
いいことである。しかしながら脳科学者というのが誰でも語れる肩書きであったり
読み手、情報の受け手側もしっかり情報を精査しなければならないわけである。
特に芸脳人と言われる人たちの著作に関しては
完全否定するわけではないけれども
全てが全て正しい
と、鵜呑みにするというのは本当に気をつけねばならないことである。
ブームというのはサイクルでその灯火が消えていく。
一過性のブームほど印象に残らないものはない。
川島教授の考えでは、この「脳ブーム」という現象が収束して終焉したにも関わらず
2015年くらいになって「脳トレ」が人々に残り続ければ「ざまあみろ!私の勝ちじゃ!」と叫べる
レベルだそうだ。
その頃にはより良い産業と学業の産学連携活動が生まれていることを
願う次第ではあります。

さらば脳ブーム (新潮新書)
川島 隆太
[詳細はAmazonで⇒ ]
]
Tweet
【後記】
どうしても「芸脳人」と呼ばれる人たちのほうが
アピールが上手だからつい表立ってしまいますが
本質を見極めるためには学術の世界で活躍されている方の本に目を向けなければ
いけないなぁなんて思ってしまった一冊です。
一時期騒がれた、ゲームで脳が破壊される
なんてことを完全否定もしているので
そのあたりにご興味ある方は読んでみても
いいかもしれないですね。
結構川島教授が毒を吐いていたので
面白く読ませていただきました。
どうでもいいですが、この乾燥する時期は
風邪の治りも悪いみたいです・・・
なかなか咳,鼻水が抜けません・・・
twitterやってますのでお気軽にfollow me↓

Presented by hiro
ブログトップへ戻る
第1章 「うかつに野に下ることなかれ」
第2章 ファミコンするより公文しろ!
第3章 学習療法を完成させる
第4章 出すぎた杭でもやはり打たれる
第5章 ニンテンドーDS「脳トレ」狂想曲
第6章 産学連携の難しさ
第7章 さらば脳ブーム
【書感】
川島教授といえば
ニンテンドーDSを持っている人であれば、このソフトを知らない人はいないのではないだろうか。

この「脳トレ」がどのように出来ていったのか、
脳トレによる「脳」ブームの功罪
そして、今の脳ブームへの喝
といった3つの視点で今回は紐解いていこうと思う。
◆学習療法を感性させるまで
結晶性知能と流動性知能というものをまず説明する必要がある。前者は、知識の正確さ、運用する能力で学校の勉強など様々、努力すればなんとかなるという域。
後者は、新しい場面や局面に対応する能力。遺伝子によって
規定されている生まれつきの能力で、20歳を過ぎたころに低下していくそうだ。
で、この流動性が確保される領域がワーキングメモリーである。
読み書きというのもこのワーキングメモリーが必要な作業で
トレーニングすることによってワーキングメモリーを鍛えることができる
と大まかに言ってしまえば、この発想から「脳トレ」は生まれている。
この読み書きを計算することによって脳を鍛えることができるのでは?
という試みを発達障害児、認知症の方たちに
向けて取り組んだということが本書には書かれている。
医療機関に行って最初に専門家たち
学習療法(読み書き計算)を取り入れようと病院へお願いするのだが
介護のプロたちには非常に冷徹な眼で見られる
「そんなことしても無駄でしょう」
って、このことはどんな研究や発明にも共通するのかもしれないですけど
最初から沢山の人々に理解されることは無い
ということなのかなと感じる。
で、いざやってみると認知症の患者さんたちは
喜んで取り組み始め、療法を続けていくうちに
問題を解く喜びを覚えたり
ある人はおしゃれをするようになったり
ある人は自律的に活動するようになったりと
凄まじい効果があったそうだ。
蓋を開けてみると川島教授の評価も「詐欺師」が「教祖様」だったそうだ。
これも新たな発明の現場では結構目につく出来事なのかもしれないけれども。
◆「脳トレ」の狂想曲
そして次に向けたのが子供の教育+大人へのドリル大人のドリルがあれば子供が机に向かっているときに大人も一緒に
解くことができる。
こういう発想が元になって、
「大人のドリル」という形で公文から発売された

このシリーズは累計400万部を突破したらしく
ドリルの内容がデータを根拠にきちんと説明されていたことや
狙い通りの子供と親の意思疎通のツールとして子供との会話が増えたなんて声も聞こえてきたり
ゆとり教育の見直しのための「朝のモジュールタイム」などの活動と偶然時期が重なったと本書では語られている。
中には、うまく導入はできたものの、高齢者の夫婦間では
こんなドリルみたいなものを俺に解かせるのか
と、プライドを逆なでてしまい、余計に認知症が悪化していった
なんて例も見られたそうだ。
これは支援者と学習者と共に学習療法を行い、学習者が教材が解けたことを
認め、お互い喜び、機会があれば教材を元に会話をするということができれば
問題のないことなのだが、伝わり方、手順が誤ってしまえば、その効果が発揮できない
という一面もあり、ちゃんとしたシステムが出来ていても
その利用方法をしっかり伝達するツール、仕組みができないと
我々が日々接している仕事という面と何ら変りないことなのかなとも感じてしまった。
とまぁ失敗の例もあるわけだが、ここから冒頭に紹介した
DSのゲームにつながっていく。
任天堂の岩田社長がDSの発売日に川島教授の研究室に訪れたなんて
エピソードが書かれている。
川島教授と岩田社長が同い年であったこと
DSと相性が良さそうということで共感し発売に至るわけである。
ただし、2点ほど落とし穴をつくったまま展開をしてしまったとも認めていて
まず、
「読み書き計算は有益である」という結論に至る過程に間違いがないことが一般の方に判ってもらえればそれで良し、としてしまった。「レフリーによるレビューを受けていないので科学じゃない」と言われてしまうと、「その通り」としか言い返せないリスクがあることを知りつつ、自分としては、一般書籍を自分の科学研究成果に並べる気持ちは全くなかったため、「まぁいいか」と妥協してしまったと
まぁここまで「脳トレ」が流行ることは想像もしていなかったということが書かれている。
もう一つは単純化した情報の露出
時の宰相であった小泉純一郎氏が、単純なフレーズを繰り返し国民に投げかけることで、国民の理解と支持をあげていく姿に学ぶことにした。読み書き計算はワーキングメモリーを必要とし、ワーキングメモリーとはこれこれを意味し、そのトレーニング効果は心理学実験ではこれこれであると、ある程度丁寧に説明することは諦め、「読み書き計算は脳を活性化し、脳を鍛える」とひどく単純な表現を繰り返し訴えることにした。ただ、このことは有名科学誌で批判されたり、先輩の科学者の方に批判されたりととんでもない目をみることになっている。
このあたりの苦労話は少々著者の愚痴っぽくなっているが
相当苦労したように見受けられるので本書を読んでね。に譲ろうと思う。
ただ、素晴らしいことはソフトの売上から入ってくる収入を個人としては一切受け取っておらず、
自分が所属する東北大学に管理してもらっているらしくビルが2棟もたったというから驚きである。
しかも、2本のDSソフトとは趣旨が異なる自分の能力向上を図る新しいソフトが2010年末に発売になる
という宣伝まで書いてある、非常に自身に満ち溢れて宣伝されているのでちょっとやってみたくもなる。
◆芸脳人をたたっ斬る
本書のタイトルである「さらば脳ブーム」の本質を語っているのが、この部分で3つといったものの、確信はこの部分ではないだろうか。川島教授は本書で「脳科学者」と名乗っている人たちを次のようにたたっ斬っている。
専門家として正々堂々とゲームに参加しているような顔をしているのが、「芸脳人」である。代表格は何と言っても、「脳科学者」茂木健一郎氏であろう。とある。確かに「芸脳人」達をたたっ斬っているわけだが、反面、正統派の研究者の方達の狭義さも知ってしまうわけである。
実際、「脳科学者」と称することには、何の資格もいらない。脳に興味があり、本の一冊を読めば、あなたが自分を「脳科学者」と呼んでも全く問題ない。うちの嫁さんも、近所のじいさんばあさんも、皆「脳科学者」になれる。芸脳人が自らを「脳科学者」と呼び、テレビに出ようが、本を書こうが、誰もそれを咎めることはできない。それでも、学者とは言えない彼らが自らを学者と呼び、自身の商品価値を高め、通訳者としての活動を行うことは、養老氏や立花氏と比べるとひどく見苦しく感じる。
本来、学者や研究者とは、人類に新しい知恵や知識をもたらす研究活動を主な生業とし、研究成果を定期的にレフリーによる査読が行われる学術雑誌や学会が主催する学術集会で発表している種族を指す言葉である。社会と学術の間を結ぶ通訳者をするにしても、研究者としての学術活動が最低9割、残りの1割弱の力を使って通訳者として働くくらいでないとインチキである。過去に一時、脳関連の研究施設にいたことがあっただけで「脳科学者」と名乗るのは、本来的にはおこがましい。
茂木氏について言えば、脳科学の先端的な研究もそれなりにフォローされているし、知見もお持ちであることは確かである。ただ、本を書いたり、講演をしたりすることが主な生業となっているなら、自分から正々堂々と「ジャーナリスト」なり「芸脳人」なりと称すれば良いのに、とは思う。そうすれば外野席の”正統派”研究者達も、表立って文句を言わなくなるであろう。
そうなると、ちょっと待って欲しい。
その情報を手にする我々に
何を信じればいいのか?
となってしまうわけである。
研究を生業にしていて、
研究に9割力を割くという研究者の方達の意見は十分わかる。
ただ、世間に伝えるために
そういったプロフェッショナルな方達が、特にニッチな分野なら尚更
しっかりと世間にメッセージを伝えてくれなければ
その研究されている方から見た
「ジャーナリスト」だとか「芸脳人」だとかが更にのさばっていくのでは
ないだろうか?
ブログだったり、Twitterだったりで
自分のメディアを持てる時代であるのだから、その1割を使って
自分メディアにパワーを割き、我々にマスゴミを通さず
真実を伝えて頂きたいものである。
学会は確かに大切かもしれない。
ただ、学会だけ、ネットなんて価値のない空間に展開しても
意味が無いなんて狭義な考え方は是非とも止めて頂きたい。
●最後に
一連の脳ブーム確かに、人が脳について、考えることについて学ぶようになったことは
いいことである。しかしながら脳科学者というのが誰でも語れる肩書きであったり
読み手、情報の受け手側もしっかり情報を精査しなければならないわけである。
特に芸脳人と言われる人たちの著作に関しては
完全否定するわけではないけれども
全てが全て正しい
と、鵜呑みにするというのは本当に気をつけねばならないことである。
ブームというのはサイクルでその灯火が消えていく。
一過性のブームほど印象に残らないものはない。
川島教授の考えでは、この「脳ブーム」という現象が収束して終焉したにも関わらず
2015年くらいになって「脳トレ」が人々に残り続ければ「ざまあみろ!私の勝ちじゃ!」と叫べる
レベルだそうだ。
その頃にはより良い産業と学業の産学連携活動が生まれていることを
願う次第ではあります。

さらば脳ブーム (新潮新書)
川島 隆太
[詳細はAmazonで⇒
 ]
]Tweet
【後記】
どうしても「芸脳人」と呼ばれる人たちのほうが
アピールが上手だからつい表立ってしまいますが
本質を見極めるためには学術の世界で活躍されている方の本に目を向けなければ
いけないなぁなんて思ってしまった一冊です。
一時期騒がれた、ゲームで脳が破壊される
なんてことを完全否定もしているので
そのあたりにご興味ある方は読んでみても
いいかもしれないですね。
結構川島教授が毒を吐いていたので
面白く読ませていただきました。
どうでもいいですが、この乾燥する時期は
風邪の治りも悪いみたいです・・・
なかなか咳,鼻水が抜けません・・・
twitterやってますのでお気軽にfollow me↓

Presented by hiro
ブログトップへ戻る

