2011年07月19日
突然ですが、林業と聞いて何を思い浮かべますか?
なんかチェーンソー使って切ったり、大変な肉体労働なのかな〜とイマイチピンとこないかもしれない。
wikipediaによると
今回の本
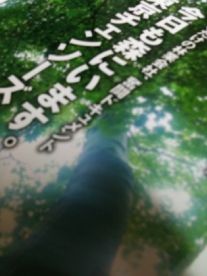
若者だけの林業会社、奮闘ドキュメント 今日も森にいます。東京チェンソーズ
青木亮輔、徳間書店取材班
[詳細はAmazonで⇒ ]
]
偶然本屋で見かけてパラパラ見てみると面白そう!と思い手にとった本なのだが、東京チェンソーズという若者だけの林業会社を起こす過程が書かれた本である。
まぁとにかく行ってみましょうか。
なんかチェーンソー使って切ったり、大変な肉体労働なのかな〜とイマイチピンとこないかもしれない。
wikipediaによると
森林に入り、主として樹木を伐採することにより木材を生産する産業。とまぁ、簡素な説明は書いてあるわけ。
今回の本
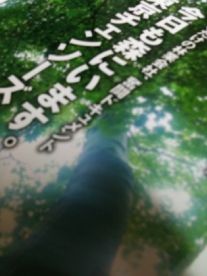
若者だけの林業会社、奮闘ドキュメント 今日も森にいます。東京チェンソーズ
青木亮輔、徳間書店取材班
[詳細はAmazonで⇒
 ]
]偶然本屋で見かけてパラパラ見てみると面白そう!と思い手にとった本なのだが、東京チェンソーズという若者だけの林業会社を起こす過程が書かれた本である。
まぁとにかく行ってみましょうか。
【目次】
【書感】
正直、林業なんてものは何のためにやっていて、何の価値があるの?とも思っていた部類なので個人的にはまったく興味のなかったジャンルである。
ただし、本書を読むまでは。
自分が育った茨城県の牛久というところは東京23区なんかに比べれば自然も豊かなところなので、それなりな田舎なのだけれども雑木林とかの木の価値とかよくわからなかったりする。
「山が育つ」という言葉がでてくるが、なかなか馴染み無い言葉である。
山が育つというのは手入れをし、適度に空間を開け、風通しをよくする。
しかし、山といっても管理を箇所箇所で別な人が行っていたりするため、別な管理会社がやっていたり、放置されたりと山全体を育てることはなかなかできないことだそうだ。
東京都と言えば都会、コンクリってイメージをしてしまうかもしれないが、
東京都の森林面積は都の総面積の4割近く、約8万ヘクタールにも及ぶそうだ。
まぁ、7割が多摩地域西部なので東側に住む自分としては、そんな恩恵は感じられないわけだがね…。
ここで出てくるのが東京チェンソーズの創業者、本書著者の青木亮輔氏である。
東京農業大学農学部林学科出身の冒険部出身で活動家。
学生時代はいろいろなところに冒険行ったりその武勇伝の紹介は本書に任せるが、まぁ活動的である。
しかし、いきなり林業に関わったかといえばそうではない、教育系教材の出版社で営業マンを務めたが、営業成績はあがらず、会社を辞し「地下足袋を履く仕事がしたい!土の感触を踏みしめるのは気持ちがいい!自然や山に関する仕事……、そうだ!林業の世界に入ろうと決めました」というのが林業に踏み出すきっかけだったとか。
それに、林業業界は若い人がいない、給料が安い、危険できついというマイナス面を林学科にいただけに普通の人よりも知っていたわけ、しかし、青木氏はネガティブにそれを受け取らずに「若い人がいないなら、若い自分が歓迎されるはず。そうした世界なら、自分を必要としてくれる、自分だからこそ、できることがたくさんあるだろうと思いましたから!」とある種ブルーオーシャンを見つけにいくわけである。
いくつか採用されたものの、結果、檜原村森林組合で働くことになる。
ただしここでの雇用は「緊急雇用対策」半年間の期限付きで社員でも
アルバイトでもないわけ(辞退したものには正社員採用もあったそうだ。)
しかし、青木氏は諦めずに肉体労働メインで必要な体づくりをして自分は体ができていることをさりげなくアピールしたり、その土地の勉強を続け、熱意が実って緊急雇用対策の期間が伸び、熱意が実って緊急雇用という立場から檜原村森林組合に正式採用される。
若い人もちらほら来るみたいだが、やっぱり著者のような情熱を持った人は稀で
「だから、理想を追い求めてやって来ても、一日や二日で音をあげてしまう人が多く、若い人材を育成したくとも、なかなか定着しない」という現実を突きつけられてしまうわけである。
しかし、そこに魅力があるのも間違いないわけで
これは何の業界、業種でもそうだと思うけれど、できるチームはガツガツやっていくし、足をひっぱる部類のものは足をひっぱる。それは向き不向きがあるからまぁ当然と言ってしまえば当然なのだが、林業にもそれと同様のことが言える場面が出てくる。
森林組合で働いているのは青木たちだけでない。複数の班で構成されるなか、仕事のスピードやクオリティに差が出てしまうのは当然で、それぞれがそれを補い合っている。しかも、待遇改善は組合全体に波及する。それだけの余裕などあるはずもない。だから、”君たちだけを特別扱いできないんだよ、わかってくれ”という結論に終わる。
こういうしがらみもあり、独立「東京チェンソーズ」となる
最初は森林組合からの請負100%だったのだが、段階的に事業を拡大するために、お客さんから直接仕事をもらうために独立してから3年で東京で4つめの「林業認定事業団体」になった。
だが、林業という業種でのボロ儲けはあり得ないわけで、サラリーマンのように毎年給料が上がることもありえない。「稼ぐ」にはバリバリ働くしかない。4人で起業したメンバー間でも経験値が各自あるとはいえ、得手不得手がある。最初は一律だった給料も、実際にやってみて個人ごとの仕事ベース、クオリティで能力給になっていったそうだ。
そしていつかは東京チェンソーズから独立して巣だっていける環境をという思いもあるそうだ。
採用するきっかけは、作業スピード、作業の正確さはもちろんのことだが、どんな山にしたいかという想像力も大切だそうだ。
これも、何かしらの仕事に就くのなら必須の考えで、理想を描き、実現していく想像力っていうのは無くてはならないものではないだろうか。
本書内に東京チェンソーズの皆様の写真がふんだんに使われているのだが、
やりがいに満ちたなんとも表現しづらい写真が多く掲載されていて元気をわけてもらえる。
林業を志さないにしても、どんな理想を描くか、それをどうやって実現するか、何を思い仕事をすればいいのか、ということがいかに大切かということが伝わってくる本である。少し迷いが出ていたり、自分の思いが薄れてしまったときにちょっと読んでみるといい一冊なのではないだろうか。
ちなみに、檜原村をgoogle earthで見てみると…
大きな地図で見る
うん、見事に森ばかりだね・・・。
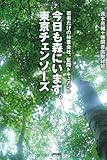
若者だけの林業会社、奮闘ドキュメント 今日も森にいます。東京チェンソーズ
青木亮輔、徳間書店取材班
[詳細はAmazonで⇒ ]
]
【後記】
今回は「林業」という観点の本だったが人気がなかろうが本質的には同じということが言える職業結構多いんじゃないかなと感じる。
情熱を持つこと、未来につながること
そういった視点を持つことって大事だなと反省する次第であります。
twitterやってますのでお気軽にfollow me↓

RSSリーダーにご登録頂けると幸いです。


Presented by hiro
ブログトップへ戻る
第1章 今日は青梅の神社の杜にいます
第2章 林業マン青木亮輔の出来るまで
第3章 青木亮輔の80%は探検部で出来ています
第4章 東京チェンソーズ誕生物語
第5章 東京の秘境桧原村で暮らす
第6章 新生東京チェンソーズの探検が始まった
スペシャル対談三浦しをん×青木亮輔
【書感】
正直、林業なんてものは何のためにやっていて、何の価値があるの?とも思っていた部類なので個人的にはまったく興味のなかったジャンルである。
ただし、本書を読むまでは。
自分が育った茨城県の牛久というところは東京23区なんかに比べれば自然も豊かなところなので、それなりな田舎なのだけれども雑木林とかの木の価値とかよくわからなかったりする。
1)東京の山事情
著者は東京での仕事をメインにしているため、東京の山事情なんてことも書いてある。林業。やっぱり本書を読む限り簡単ではないし、肉体労働であることはまちがいないことである。現場まではトレッキングなんて言って取材をしたスタッフもヒーヒーだったそうな。「山が育つ」という言葉がでてくるが、なかなか馴染み無い言葉である。
山が育つというのは手入れをし、適度に空間を開け、風通しをよくする。
しかし、山といっても管理を箇所箇所で別な人が行っていたりするため、別な管理会社がやっていたり、放置されたりと山全体を育てることはなかなかできないことだそうだ。
東京都と言えば都会、コンクリってイメージをしてしまうかもしれないが、
東京都の森林面積は都の総面積の4割近く、約8万ヘクタールにも及ぶそうだ。
まぁ、7割が多摩地域西部なので東側に住む自分としては、そんな恩恵は感じられないわけだがね…。
2)若い人がいない、安い、危険な林業の世界へ
何度も言うが、林業と聞いても?と思ったり正直、仕事のイメージもしずらい世界である。ここで出てくるのが東京チェンソーズの創業者、本書著者の青木亮輔氏である。
東京農業大学農学部林学科出身の冒険部出身で活動家。
学生時代はいろいろなところに冒険行ったりその武勇伝の紹介は本書に任せるが、まぁ活動的である。
しかし、いきなり林業に関わったかといえばそうではない、教育系教材の出版社で営業マンを務めたが、営業成績はあがらず、会社を辞し「地下足袋を履く仕事がしたい!土の感触を踏みしめるのは気持ちがいい!自然や山に関する仕事……、そうだ!林業の世界に入ろうと決めました」というのが林業に踏み出すきっかけだったとか。
それに、林業業界は若い人がいない、給料が安い、危険できついというマイナス面を林学科にいただけに普通の人よりも知っていたわけ、しかし、青木氏はネガティブにそれを受け取らずに「若い人がいないなら、若い自分が歓迎されるはず。そうした世界なら、自分を必要としてくれる、自分だからこそ、できることがたくさんあるだろうと思いましたから!」とある種ブルーオーシャンを見つけにいくわけである。
いくつか採用されたものの、結果、檜原村森林組合で働くことになる。
ただしここでの雇用は「緊急雇用対策」半年間の期限付きで社員でも
アルバイトでもないわけ(辞退したものには正社員採用もあったそうだ。)
しかし、青木氏は諦めずに肉体労働メインで必要な体づくりをして自分は体ができていることをさりげなくアピールしたり、その土地の勉強を続け、熱意が実って緊急雇用対策の期間が伸び、熱意が実って緊急雇用という立場から檜原村森林組合に正式採用される。
若い人もちらほら来るみたいだが、やっぱり著者のような情熱を持った人は稀で
「だから、理想を追い求めてやって来ても、一日や二日で音をあげてしまう人が多く、若い人材を育成したくとも、なかなか定着しない」という現実を突きつけられてしまうわけである。
しかし、そこに魅力があるのも間違いないわけで
「山の仕事はすぐに結果が見えるものではありませんが、たとえば、思った方向に木を倒したときの手応えや、鬱蒼とした森を間伐して、そこに光と風が入ると、たまらない爽快感があります。という著者の言葉は熱いなぁと感じ取れる部分でもあります。
でも、そこに下草が生えて根付き、木が生長し木材となるまでには長い年月が必要です。そうした木、林、森、山のサイクルは僕の代だけではない、僕ら以前から、僕たち、そして次の世代へと受け継がれていくものなんです。」
3)何でもかんでも平等はNG、だからこその独立
仕事は個人のスキルに依存する部分が多々ある。これは何の業界、業種でもそうだと思うけれど、できるチームはガツガツやっていくし、足をひっぱる部類のものは足をひっぱる。それは向き不向きがあるからまぁ当然と言ってしまえば当然なのだが、林業にもそれと同様のことが言える場面が出てくる。
森林組合で働いているのは青木たちだけでない。複数の班で構成されるなか、仕事のスピードやクオリティに差が出てしまうのは当然で、それぞれがそれを補い合っている。しかも、待遇改善は組合全体に波及する。それだけの余裕などあるはずもない。だから、”君たちだけを特別扱いできないんだよ、わかってくれ”という結論に終わる。
こういうしがらみもあり、独立「東京チェンソーズ」となる
最初は森林組合からの請負100%だったのだが、段階的に事業を拡大するために、お客さんから直接仕事をもらうために独立してから3年で東京で4つめの「林業認定事業団体」になった。
だが、林業という業種でのボロ儲けはあり得ないわけで、サラリーマンのように毎年給料が上がることもありえない。「稼ぐ」にはバリバリ働くしかない。4人で起業したメンバー間でも経験値が各自あるとはいえ、得手不得手がある。最初は一律だった給料も、実際にやってみて個人ごとの仕事ベース、クオリティで能力給になっていったそうだ。
そしていつかは東京チェンソーズから独立して巣だっていける環境をという思いもあるそうだ。
採用するきっかけは、作業スピード、作業の正確さはもちろんのことだが、どんな山にしたいかという想像力も大切だそうだ。
これも、何かしらの仕事に就くのなら必須の考えで、理想を描き、実現していく想像力っていうのは無くてはならないものではないだろうか。
●最後に
その他にも東京チェーンソーズが活動している檜原村での自炊、自給自足、自然豊かという生活が書かれていて、東京にもこんな場所あるんだと思いつつ、ちょっと林業という業界に対する見方が変わる1冊であることは間違いないだろうと感じ取れる。本書内に東京チェンソーズの皆様の写真がふんだんに使われているのだが、
やりがいに満ちたなんとも表現しづらい写真が多く掲載されていて元気をわけてもらえる。
林業を志さないにしても、どんな理想を描くか、それをどうやって実現するか、何を思い仕事をすればいいのか、ということがいかに大切かということが伝わってくる本である。少し迷いが出ていたり、自分の思いが薄れてしまったときにちょっと読んでみるといい一冊なのではないだろうか。
林業は衰退して久しいと言われているが、自分だったら活性化させることができるかもしれない。子どもたちに、”林業ってかっこいいよね””林業マンになりたい”と憧れと可能性を持ってもらえるかもしれない。この言葉も著者の本書内の言葉だが、こういう未来を語れる仕事を胸を張ってやりたいものである。
ちなみに、檜原村をgoogle earthで見てみると…
大きな地図で見る
うん、見事に森ばかりだね・・・。
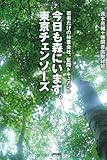
若者だけの林業会社、奮闘ドキュメント 今日も森にいます。東京チェンソーズ
青木亮輔、徳間書店取材班
[詳細はAmazonで⇒
 ]
]【後記】
今回は「林業」という観点の本だったが人気がなかろうが本質的には同じということが言える職業結構多いんじゃないかなと感じる。
情熱を持つこと、未来につながること
そういった視点を持つことって大事だなと反省する次第であります。
twitterやってますのでお気軽にfollow me↓

RSSリーダーにご登録頂けると幸いです。


Presented by hiro
ブログトップへ戻る

